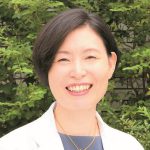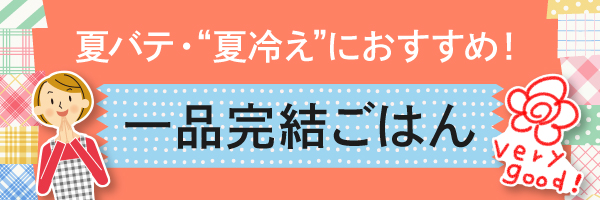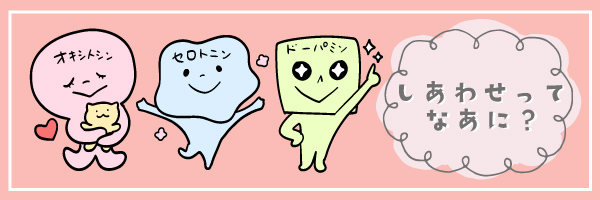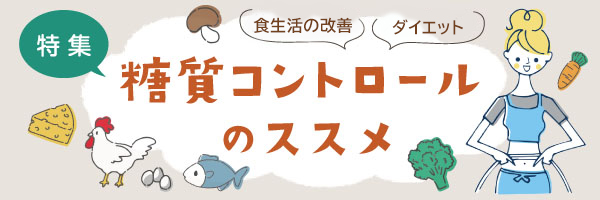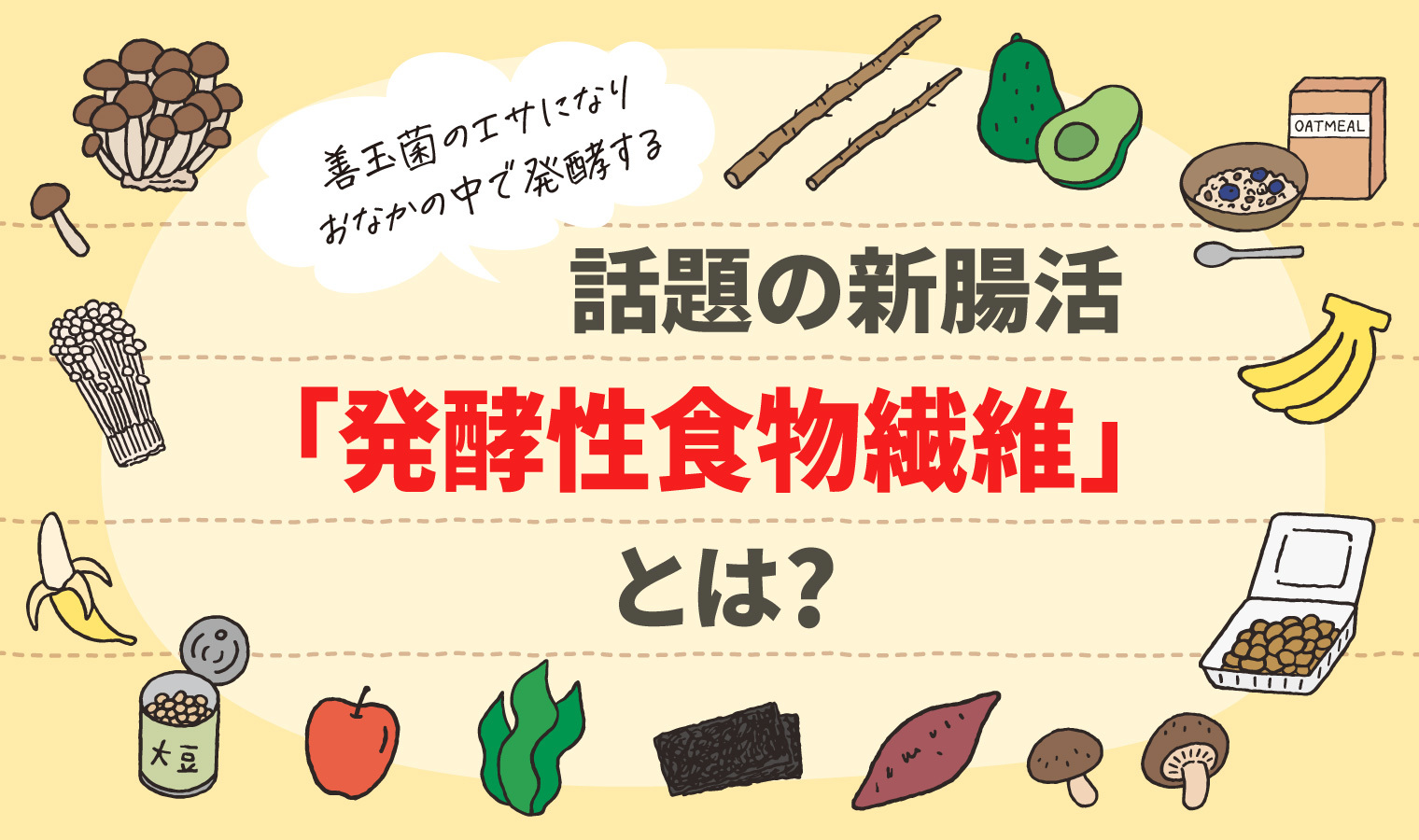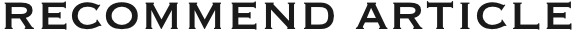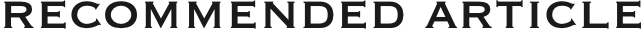タイプ別「毒なし生活」でお腹スッキリ!有害物質を体に入れないケア
食べ過ぎのほか、抗生物質や食品添加物などの有害物質を摂ると、肝臓の負担になり、代謝が低下します。それらを体に入れない「毒なし生活」で、肝臓が元気に! お腹周りもすっきりしますよ。
体に毒を入れない工夫で肝臓の代謝・解毒力UP!
それほど太っていないのにお腹に脂肪が付いている人は、肝臓の働きが低下している可能性があります。
「口から入った食べ物は、肝臓で代謝されることによって栄養素として使われます。薬も酵素によって肝臓で代謝され、体の中で使われた後は必ず肝臓を通って排泄されます。そのため、過食はもちろん、薬や体質に合わないサプリを飲めば飲むほど肝臓に負担がかかり、代謝力が落ちます」と言うのは、内科医の内山葉子さん。
「肝臓でうまく脂肪を分解できないと、腸の周りに内臓脂肪がたまりやすくなります。さらに、肝臓の解毒作用が低下することで、体内に食品添加物や農薬、化学物質などの有害物質が蓄積されます」
まずは、肝臓が弱る原因を把握すること。そして、肝臓の負担を減らす食べ方や毒を入れない食品を選びましょう。肝臓を効果的に元気にすることができ、お腹太りも解消されますよ!
あなたはどのタイプ? 肝臓が弱る原因をチェック
肝臓が弱る原因は日頃の食習慣のなかに。コツコツ毒を減らしていきましょう!
タイプA:薬やサプリをよく飲むタイプ

頭痛や肩コリのたびに、気軽に痛み止めを服用しがち。解熱・鎮痛剤や抗生物質など、あらゆる薬は肝臓の負担を大きくする要因です。漢方薬やサプリメントも、むやみに飲むと肝障害を引き起こす可能性があるので注意。
タイプAの人は…

風邪のときは、はちみつを食べるとのどの痛みが和らぐ
風邪になると鼻やのどの粘膜が細菌などによって炎症を起こします。のどの痛みやせきには、スプーン1杯分のはちみつをなめて。はちみつには殺菌作用や粘膜を保護する効果があります。

生理中・頭痛のあるときは、鎮痛剤を飲む前に体を休めてあげる
頭痛や生理痛の薬は肝臓の大きな負担に。痛みがあるときは、なるべく仕事や家事をせず、ゆっくり休むと痛みは軽減します。首や肩のコリをほぐしたり、下腹部を温めたりするのも◎。

タイプB:加工食品大好きタイプ

安くて便利な冷凍食品やレトルト食品ですが摂りすぎはNG。加工食品に使われているさまざまな食品添加物は、肝臓にダメージを与える有害物質。ホルモンバランスを乱し、慢性疲労や体調不良、うつなどの原因になることも。
タイプBの人は…

農薬やプラスチック容器、食品添加物に気を配る
野菜は日頃よく購入する1〜2種類だけでも無農薬のものに替え、調味料はビンや紙パックに入ったものに。食品添加物の少ないものを選ぶことも大切。加工食品なども控え、口から取り込む有害物質を最小限に。


タイプC:食べすぎ・飲みすぎタイプ

つい食べすぎてしまったり、食べるのがやめられなかったり……。たとえ食事の内容が良くても食べすぎてしまう人は要注意。肝臓の代謝が追いつかなくなり、肝臓に中性脂肪がたまる脂肪肝や、心筋梗塞などのリスクが上がります。
タイプCの人は…

軽めの食事と梅干しで疲れた肝臓をいたわる
肝臓をいたわるためには、「もう少し食べたいな」と感じる腹八分目を意識して。月に1度、週末だけのプチ断食をするのも手。また、肝臓の代謝機能を助ける成分が豊富な梅干しを1日に2〜3個、食前に食べると肝臓が元気に!

これもおすすめ! 苦味のある春野菜
菜の花やふきのとうなどの春野菜の苦味成分には解毒作用があり、肝臓の機能を高めます。

撮影/神尾典行 モデル/中世古麻衣 イラスト/ふるやますみ
(からだにいいこと2022年4月号より)

ふだん何気なく口にする食べ物。実は表示以外にも、非表示の添加物や農薬などの化学物質を含んで…
[ 監修者 ]