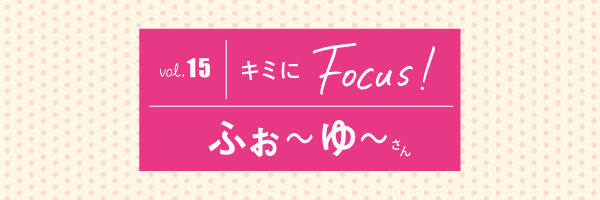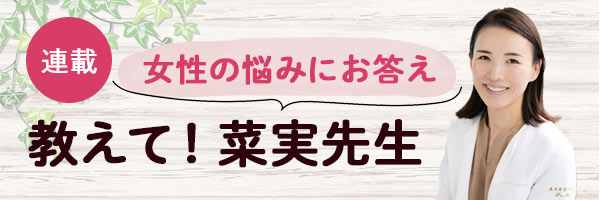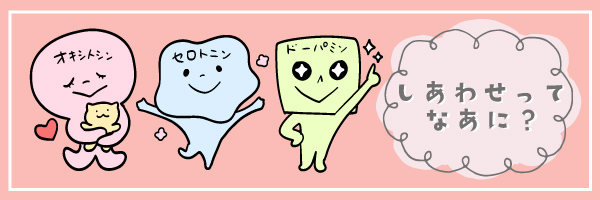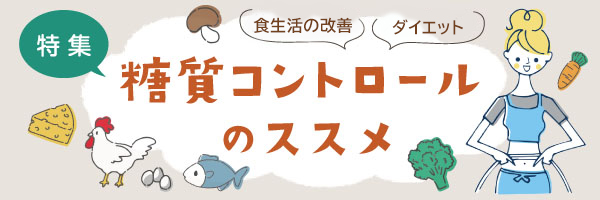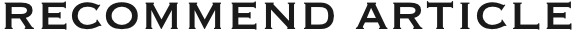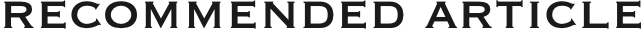東洋医学の「気・血・水」とは?体質チェックで不調の原因がわかる|田中友也さん 季節の養生法
神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」の田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は、東洋医学の「気・血・水」がテーマ。健康な体を維持するために欠かせない3つの基本要素を、くわしく解説します。
目次
東洋医学の「気(き)・血(けつ)・水(すい)」とは?
この連載で何度もご紹介してきたのが、東洋医学の養生の基本となる「気(き)・血(けつ)・水(すい)」。東洋医学では、五臓(肝〈かん〉・心〈しん〉・脾〈ひ・胃腸〉・肺〈はい〉・腎〈じん〉)が正常に働いていることが、不調のない健康な状態とされます。気・血・水はその状態を保つために必要で、車でいうとガソリンのようなもの。
気・血・水の3要素は、体の中を巡り、私たちの生命活動を担っています。これらは多すぎても少なすぎてもよくありません。過不足も、滞りもない状態が理想的。バランスよく働いていることが重要で、どれかが不足したり、滞ったりしてそのバランスが崩れると、不調があらわれたり、病気の原因になったりします。
気・血・水の3つは、いつまでも健康でいるために、休みなく心身を支えてくれているのです。それでは、それぞれの役割を解説していきます。

「気」は活動のためのエネルギー
「気」は、活動するために必要な目には見えないエネルギー。「最近疲れやすいな…」「朝なかなか起きられない」といったよくあるプチ不調も、気が関係しています。気には、次の6つの働きがあります。
(1)推動(すいどう)作用…体(内臓や生命力など)を成長させたり、気血を巡らせたりする働き。
(2)温煦(おんく)作用…体を温めて体温を一定の高さに保つ働き。臓器や組織を温めて活動を促進する。
(3)防衛作用…免疫機能を維持し、細菌やウイルス、気候や気圧の変化など、外界の邪気から体を守る働き。
(4)固摂(こせつ)作用…汗を止める、出血を止めるなどの血や水をとどめる作用、内臓をあるべき場所に保持する働き。
(5)気化作用…体にあるものを他のものに作り替える働き。気を血に作り替える、水が代謝により汗や尿に変化するなど。
「血」は血液や栄養。精神活動にも関係
「血」は、体を流れる赤い液体のことで、血液やそれに含まれる栄養素も含まれます。体を構成して生命活動を維持し、全身に栄養を与える働きがあります。
そのほか、東洋医学独特の考え方として、血は精神・意識・メンタルにも密接に関わっています。何かを考えたりするときにも使われ、精神的な活動も血が支えています。
「水(津液・しんえき)」は体のうるおい
「水」は、東洋医学で「津液(しんえき)」ともいわれ、血液以外の正常な水分をあらわします。例えば、唾液、汗、リンパ液、脳を流れる脳脊髄液、皮膚のうるおい、そのほか体を流れる液体。これらすべてが水(津液)で、体をうるおす働きと、体の熱を冷ます働きがあります。
津液の「津(しん)」は、サラサラした液体で、筋肉や皮膚など体の浅い部分を流れるもの。例えば、空気が乾燥して肌が乾燥するのは、津の不足が関係しています。
一方「液(えき)」は、ネバっとしている液体で、関節や頭蓋骨など体の深い部分を流れるもの。例えば、加齢によって関節が動きにくくなるのは、液の不足によるものです。
年齢を重ねると「気・血・水」が不足しやすい
気・血・水は、若い頃と比べて年齢を重ねると過不足や滞りが起こりやすくなります。基本的には、いずれも不足する傾向にあり、巡りも滞りがちに。
気・血・水をつくるための要は「脾(胃腸)」ですが、加齢で内臓の働きが衰え、十分につくり出せなくなることによっても起こります。血液がドロドロになったりむくみやすくなることも、加齢による滞りが関係しています。
「気・血・水」不足はどれくらい?体質タイプをセルフチェック
気・血・水のうち、「何が不足しているのか・滞っているのか」を知ることは、今ある不調の根本原因を突き止めるヒントになります。
気・血・水にはそれぞれ、「不足タイプ」「滞りタイプ」があり、合計6つのタイプがあります。ご紹介する6つのうち、最も数多く当てはまったものが、あなたの体質タイプ。
あわせて紹介する養生法を実践して、生活習慣を整え、体質改善していきましょう。2番目に数が多かったタイプも、体質として持っていますので、そちらの養生法も参考にしてみてください。

気の不足タイプ(気虚・ききょ)
□疲れやすい
□朝起きられない
□ダルさがとれない
□冷え性
□息切れしやすい
□汗をかきやすい
□食後に眠くなる
□胃腸が弱く、下痢しやすい
□風邪をひきやすい
□集中力が持続しない
気の不足タイプ(気虚)の養生法
気の不足は「気虚(ききょ)」といい、疲れやすさや冷え、胃の不調などがあらわれやすくなります。食事は、脂っこくて味付けの濃い食事、甘い物、冷たいものをできるだけ避けること。体を冷やさないようにする、睡眠時間を確保することも心がけましょう。
気の滞りタイプ(気滞・きたい)
□怒りっぽく、いつもイライラしている
□ゲップ、おなら、ため息が多い
□生理前に不調が出やすい(PMS〈月経前症候群〉)
□喉がつまったような感覚がある(梅核気・ばいかくき)
□緊張やストレスがかかると体調が悪くなる
□情緒が不安定
□下痢や便秘を繰り返す
□お腹や胸、頭が張るように痛い
□寝つきが悪く、途中で目が覚める
□食欲にムラがある
気の滞りタイプ(気滞)の養生法
気が滞ることを「気滞(きたい)」といい、メンタル不調や不眠にも影響します。友だちと話したり、歌を歌ったりして、ストレスを外に発散するのがおすすめ。予定を詰め込み過ぎず、余裕をもって生活することが、体調を整えるコツです。髪のブラッシング、頭を揉むことも気を巡らせるのに効果的。
血の不足タイプ(血虚・けっきょ)
□めまいや立ちくらみがある
□眠りが浅い
□かすみ目や疲れ目
□不安感が強い
□実年齢よりしわが多く、老けて見られやすい
□髪が細く、抜けやすい
□顔色が悪い、青白い
□考えがまとまりにくい
□爪が割れやすい
□年中乾燥肌
血の不足タイプ(血虚)の養生法
血の不足は「血虚(けっきょ)」といい、目の不調、眠りに関係するほか、肌や髪など美容面にも影響があらわれます。血を補うために一番意識したいのが、睡眠。血を消耗させる目や頭の使いすぎにも注意して、無理なダイエットもやめましょう。
血の滞りタイプ(瘀血・おけつ)
□頭痛(刺すような痛み)
□生理痛(塊が出る、寝込むほどの激痛)
□シミやそばかす、あざができやすい
□目の下にクマができやすい
□ゴツゴツしたニキビ跡がある
□マッサージによく行き、行くと楽になる
□肩こり(いつも決まった場所がこる)
□顔色のくすみ
□手足が冷える
□唇、歯ぐき、舌の色が暗い
血の滞りタイプ(瘀血)の養生法
血の滞りは「瘀血(おけつ)」といい、頭痛や生理痛、肩こりなどの痛み、肌トラブルなどにつながります。このタイプは、体を冷やさないこと、適度に体を動かして運動不足を解消することが大事。デスクワークの人は長時間同じ姿勢にならないようにして、血を巡らせます。
水の不足タイプ(陰虚・いんきょ)
□のどが乾きやすい
□よく寝汗をかく
□めまい、かすみ目
□微熱っぽい
□やせ型
□手のひらや足の裏が熱い
□動悸
□頬が赤くなりやすい
□便秘かコロコロうんち
□ほてりやのぼせを感じる
水(津液)の不足タイプ(陰虚)の養生法
水(津液)の不足は「陰虚(いんきょ)」といい、体の乾きを感じやすく、熱がこもった状態になります。ほてりやのぼせがある人もこのタイプ。うるおいを補うには、十分な睡眠が基本。激しい運動や岩盤浴など、汗をかきすぎる習慣は逆効果に。
水の滞りタイプ(痰湿・たんしつ)
□全身が重だるい
□肥満、または水太りで体がプヨッとしている
□雨の日に体調が悪い
□甘いもの、脂っこいもの、おいしいものが好き
□食欲がない、味がしない
□手足がむくみやすい
□めまい、吐き気
□胃がムカムカしやすい
□胸のつかえ感や痰がよく出る
□下痢や軟便が多い
水の滞りタイプ(痰湿)の養生法
水(津液)の滞りは「痰湿(たんしつ)」といい、体に水がたまることでだるさや雨の日の不調、むくみなどが生じます。水(津液)を巡らせるには、ストレッチやウォーキングなどで軽く汗をかく運動を。過剰に水を飲まないこと、暴飲暴食を避けた食事を心がけてください。
今月の養生ポイント:自分の体質と養生法を知って健康に
生命活動の維持に欠かせない気・血・水の3要素は、加齢によって過不足や滞りが起こりやすいとお伝えしました。それ以外に、季節や1日の中でも変化があります。
例えば、生活環境が変わることの多い春や、長期休暇のある夏休み明けなどはストレスが多くなり、気が滞りやすくなります。水(津液)は、湿気の多い梅雨時期は滞りやすく、空気が乾燥する秋・冬は不足気味に。
また、1日の中だと、気・血・水がもっとも充実しているのは、睡眠から目覚めた朝。夕方頃に体がしんどくなってくるのは、朝は満タンだったそれらが消耗するからです。
このように、季節や時間帯との関係、自分の体質タイプ、補うための養生法を知っておくことが、不調のない元気な体づくりのカギになります。「体調がいまいちかも」と思ったときこそ、気・血・水を補う生活を思い出して、実践してみてください。
取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ