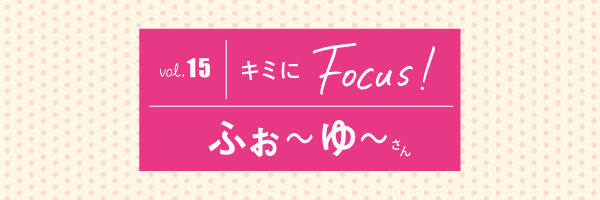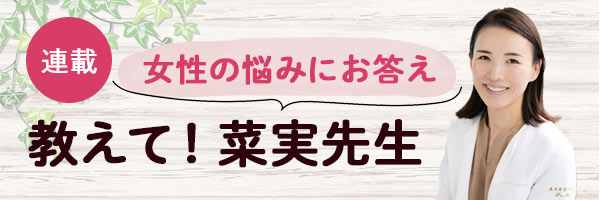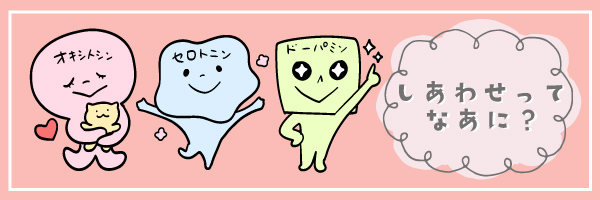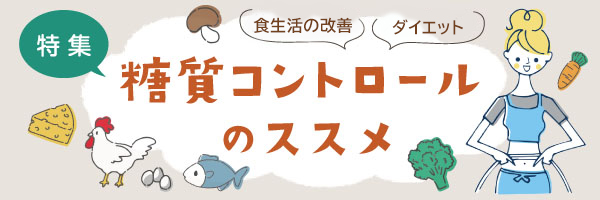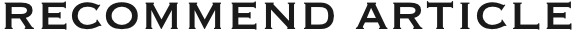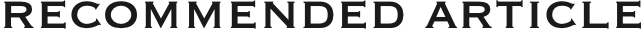“腎”を鍛えてストレスと不眠を撃退する「塩こんぶキャベツ」
疲れやすい、体が重い、不眠やストレスを抱えている…。そんな人は腎臓や副腎が弱っているかも。解毒力の高いキャベツと抗酸化作用を持つ塩こんぶの組み合わせが、弱った“腎”を元気にしてくれます。
目次
腎臓と副腎が元気になればストレス解消!
「腎臓と副腎は、心と体を守る要。胃腸や肝臓の機能が落ちたり、血管に炎症が起こったりすると、腎臓や副腎に負担がかかり、疲弊してしまいます。そのため、腎活には胃腸や肝臓、血管のケアが不可欠です」と、薬剤師・国際中医師の大久保 愛さん。
また、ストレスから身を守る働きがある副腎は、精神的ストレスや寒暖差などの身体的ストレスを受けると、抗ストレスホルモンを分泌し続けて疲れ切ってしまうそう。
「キャベツの解毒力と塩こんぶの抗酸化作用で、胃腸や肝臓の不調を改善。食前に摂ることで血糖値の急上昇を防いで血管の炎症を抑え、腎臓と副腎のダメージを防止します」
ストレスから心身を守る副腎が元気になることでメンタルも安定します。すると、夜に深く眠れるようになり、心身の疲れが取れやすく。また、腸内環境が整うと自律神経が乱れにくくなることもわかっています。さらに、よく噛むことで幸せホルモンが分泌される効果も。
「Mサイズの密閉袋1つ分を、1日で食べ切るのがおすすめ。簡単に作れて、無理なく続けられますよ」
キャベツと塩こんぶの健康パワーがダブルで得られる

それぞれ単体でもさまざまな長所を持つキャベツと塩こんぶ。その2つを掛け合わせることで、おいしさもメリットも増えます。作り方が簡単なのも続けやすいポイント。
キャベツの健康効果

- 肝機能が回復して腎臓の負担が減る
抗酸化成分「スルフォラファン」が、肝臓のデトックス機能をサポート。腎臓にかかる負担を減らします。 - 胃腸が元気になって解毒力が向上する
「キャベジン」が胃の粘膜を修復し、不溶性食物繊維が便秘を改善。胃腸の消化吸収力と解毒力がアップ。 - 血管の炎症やイライラを防ぐ
キャベツから食べ始めることで、血糖値の急上昇を抑制。 血糖値の乱高下による血管の炎症やイライラを防止。 - 水と熱を排出してだるさを改善
体内に停滞していた余計な水分と熱を排出。むくみやほてりが改善され、体の重だるさを和らげます。
塩こんぶの健康効果

- 抗酸化作用で細胞を守る
強い抗酸化作用をもつ「フコキサンチン」が、細胞を傷つける活性酸素から内臓や血管を守ります。 - 副腎を癒やしストレスに強くなる
マグネシウムやカルシウムなどのミネラルが、弱った副腎を回復。抗ストレス作用や免疫力を高めます。 - 腸内環境を整えメンタルも安定
水溶性食物繊維が腸内環境を整え、排便を促進。自律神経のバランスも整い、イライラや落ち込みも緩和。 - 丈夫な血管と心の健康を保つ
豊富なうまみ成分で減塩でき、血管の健康をキープ。よく噛むことでうまみが増し、幸せホルモンが分泌。
塩こんぶキャベツの作り方

キャベツ約1 / 4個を大きめにちぎり、Mサイズの密閉袋にぴったり収まる量を入れる。塩こんぶ大さじ1を加えて袋を閉じ、キャベツの繊維を壊すように全体をしっかりもむ。
楽しい? 体にいい? 食事は目的を決めて
副腎はストレスから身を守る一方、過度なストレスによって疲れ切ってしまう、という話がありました。実は「食べ方」そのものにも、ストレス解消の糸口があると大久保さんは言います。
「健康を意識して食事をするのは悪いことではありませんが、それだけを目的にすると疲れますし、食べる楽しみが減ってしまいます。おすすめは、食べる前に食事の目的を決める方法。この食事は『楽しい』『体にいい』のどちらなのかをあらかじめ決めて食べるのです」

例えば、どうしても食べたい限定スイーツがあって、食べることで自分の幸福度がアップすると感じるなら、「楽しい食事」として目いっぱい堪能しましょう。今日「楽しい」を選択したら明日は「体にいい」を優先して自炊するなど、バランスを取ればOK。
食べる目的をあらかじめ明確にすることで、「なんとなくカロリーを摂取してしまった」「食べたら良くないとわかっているのに食べてしまった」といった罪悪感を減らし、ストレスを感じずにすみます。
朝ごはんを食べると「腎」が整う
「朝が弱くて朝食がとれない」という人は、東洋医学の「腎」が弱っているかも。
朝食を抜く理由の多くは、前日の夕食時間が遅かったり、脂っこいものをたくさん食べていたりするせい。胃腸に負担がかかって眠りの質が下がった結果、生命力の源とされる腎が弱くなってしまうのです。
朝昼晩の食事量は朝が一番多く、夜になるにつれて減っていくのが理想。また、起床してから1時間以内に朝食、14時間以内に夕食をとると体内時計に良い影響が。夕食は22時までには食べ終えるようにしましょう。
体内時計を整える食材
朝:朝食のボリュームは多くてOK。日中に受けるストレスに対抗するために、抗酸化力のあるポリフェノールを含む野菜がおすすめ。また、筋肉を作る時間帯でもあるため、たんぱく質をしっかりとることも意識して。

【おすすめ食材】トマト、かぼちゃ、にんじん、緑茶、セロリ、こんぶ、鮭、卵、鶏肉、キムチなど
夜:良質な睡眠のためにキャベツや大根など消化の良い野菜を。たんぱく質は脂質の少ないものを選び、できれば夕食は腹7分目に。午後はミネラルの吸収率が高まる時間帯なので、積極的に摂取を。

【おすすめ食材】きのこ、小松菜、キャベツ、大根、ひじき、えび、いか、たこ、豚肉、豆腐、納豆など
食事で体内時計が整い、毎日朝ごはんをしっかり食べられるようになると、腎の働きも良くなります。
無理なく続く健康法や食習慣を選んで
健康になりたいからと食生活がストイックになりすぎたり、極端な糖質制限などをするのは良くない、と大久保さん。“やりすぎ”は長続きせず、反動でマイナスになることもあるからです。
「そんなときこそ、まずは塩こんぶキャベツ。手に入りやすい食材でコスパも良く、続けやすいと思います。また、ほかの食べ物を制限するようなものではないため、食べる楽しみを失わずにすみます」
体調に不安があるときや体を整えたいときに、塩こんぶキャベツが強い味方になりますよ。
取材・文/籔智子、編集部 イラスト/カツヤマケイコ
(一部、からだにいいこと2025年2月号より抜粋)
『からだにいいこと』2月号では「腎活特集」を掲載。腎臓が元気になる健康法のほか、ハミ肉にサヨナラできるダイエット企画や美肌になれる美容法など、気になる記事が盛りだくさんです!

Amazon.co.jp: からだにいいこと 2025年2月号 [雑誌]
からだにいいこと キャンペーン | 雑誌/定期購読の予約はFujisan
編集部公式SNSでも情報発信中
Instagram編集部公式アカウント
X(旧Twitter)編集部公式アカウント
[ 監修者 ]