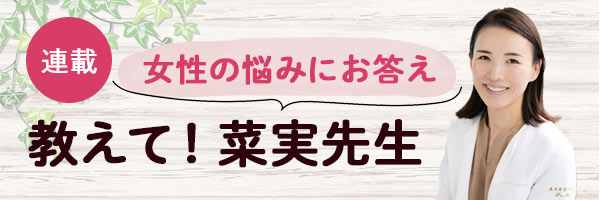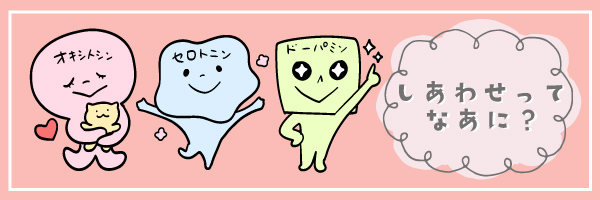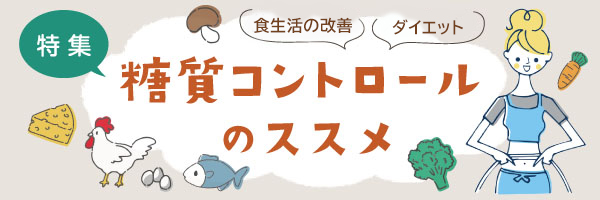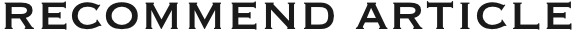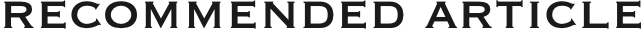骨を刺激する「なわとびステップ」で、脂肪も糖もメラメラ燃える!
更年期前後からの太りやすくなるお悩みに、かかとの骨を刺激する「なわとびステップ」がおすすめ。脂肪や糖を燃焼させるホルモンがしっかり分泌され、骨も丈夫になって、全身の老化予防効果も!
適度な骨への刺激で、若々しい体を取り戻せる
「骨を適度に刺激すると、新たな骨が作られます。その際に臓器を活性化させる“骨ホルモン”が分泌され、更年期・閉経後の女性を元気にします」と話すのは、整形外科医の山本慎吾さん。
骨ホルモン「オステオカルシン」の働きのひとつが、男性ホルモンの活性化。欧米では、更年期症状が改善しない人に男性ホルモンを補充する治療が行われているとか。
「男性ホルモンが活性化しても男性化するわけではないので、ご安心を。男性ホルモンには、内臓脂肪の増加を抑え、脂肪や糖の代謝を上げる効果があります」

1. 骨に刺激が加わることによって、新しい骨が作られます。かかとで床をたたく程度の軽い刺激でも、骨の新陳代謝が活発に。
2. 新しい骨が作られることで、骨ホルモン「オステオカルシン」の分泌量もアップ。産生された骨ホルモンの一部が血液中に放出され、全身の血管を巡ります。
3. 骨ホルモンが全身を巡ると臓器が元気に。脂肪や糖の代謝がアップします。男性ホルモンも活性化し、内臓脂肪の蓄積を抑制。やる気も上がり活動的に!
「同時に女性ホルモンの低下で起こる不調や気力の低下も緩和するので、特に更年期後期からは骨ケアを取り入れてほしいですね」
さらに骨に刺激を与えることで新しい骨が生成されるので、閉経後に急激に低下する骨密度のケアも同時に可能になる嬉しいエクサです。お気に入りのBGMに合わせて、楽しくかかとをトントンしてみて!
骨活「なわとびステップ」のやり方

1. ひざを内側に向けてかかとで床を軽くたたく
右ひざを内側に向けて、右足のかかとで床を軽く15回たたきます。なわとびをするようにリズミカルに。好きな音楽を聴きながら行うのもおすすめです。続いて左足も同様に。

2. ひざを外側に向けてかかとで床を軽くたたく
次に、右ひざを外側に向けて、右足のかかとで床を軽く15回たたきます。脚の付け根を内外にしっかり動かすことで血流が促進され、骨ホルモンも全身を巡るように。左足でも同様に行います。
骨活「なわとびステップ」を続けるといい理由は?
“骨刺激”の継続で骨ホルモンが全身をスムーズに巡るようになり、多くの臓器の働きが活発に。体の老化によるさまざまな症状を予防&改善してくれます。



手を組んで首の付け根に当て、ひじを開閉しながら頭頂部に向かって動かし、頭を刺激。手のひらで頭をグッと押して。23個の骨で構成されている頭蓋骨が刺激され、効率的に骨ホルモンが分泌されます。
撮影/神尾典行 モデル/川野由架子
(からだにいいこと2021年2月号より)
[ 監修者 ]