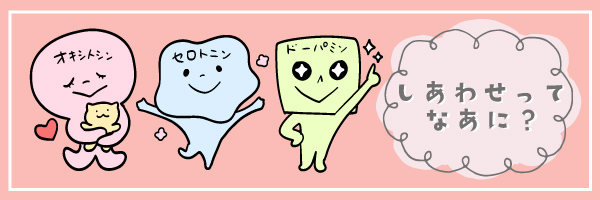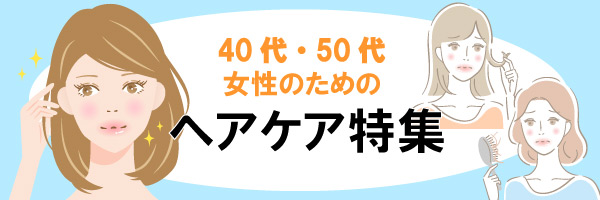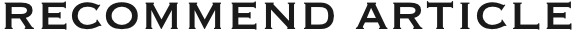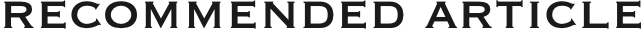「当たり前の日々」が、輝かしい毎日だと知りました|病が教えてくれたこと
直腸ガン、肺への転移、計4回の手術――。20代で生死の境をさまよった読者の中村裕子さん。健やかな心身を取り戻すまでの15年間を語ります。
目次
インタビューに答えてくれたのは:中村裕子さん(仮名)
からだにいいこと読者の中には、「病がきっかけで健康と向き合うようになった」という女性がたくさんいらっしゃいます。そんなご自身の闘病体験をお話しいただく、新連載がスタート。今回、インタビューに答えてくれたのは、読者の中村裕子さん(仮名)です。

1978年生まれ。2005年、27歳で直腸ガンを発病。07年には両肺への転移が判明、2年で計4度の手術を経験。その後10年通院を継続。2017年、完全快癒を告げられ通院を終了。
腹痛がきっかけで受診、20代でガンが発覚
スポーツ好きで活動的な、「ごく普通の20代」だった中村裕子さん(仮名)が、体調に異変を感じ始めたのは2005年の春のことでした。
「食事のたび、なぜか腹痛がありました。でも、数件行ったクリニックではどこも『異常なし』。大腸の内視鏡検査を受けたのは、それから半年後です。先生の表情があきらかに曇り、総合病院への紹介状を渡されました。でも私はあまり深刻に捉えていなくて…この後の展開を、まるで予想していませんでした」
「生存率2割」に打ちのめされて

総合病院の診断は「悪性の可能性あり」。開腹手術で腫瘍を取り出して調べることになり、11月に最初の手術を受けることに。
「それでもまだ、実感はわかず。手術直前、先生が私のお腹にマークを書き入れながら『人工肛門をつけるかも』とおっしゃったときでさえ、たぶんつけないだろう、と思っていました。だから麻酔から覚めたとき、お腹についている『何か』が人工肛門だとわかって…言葉にならないほど、ショックをうけました。
さらに一週間後、腫瘍が悪性だと判明。ステージは『4に近い3』、しかも転移性のガンだ、と。抗がん剤治療が不可欠で、全5クールのうち1クール目は入院中に開始、並行してストーマ(人工肛門の器具)の使い方も習う…と話が次々に振ってきて、ただ呆然とするのみです。
現実感がわいたのは、自分で本を読んで調べたときです。私の状態は『五年後の生存率が20%』という数字に打ちのめされました。
私、死ぬの?なんで私だけがこんな目に!? 恐怖と絶望が渦巻いて、真夜中、布団の中で泣きました」
「当たり前」を取り戻したい
抗がん剤投与の開始後は、副作用に苦しむ毎日。そんな日々の支えになったのは、同じ病気の患者さんたちとの交流でした。

「治療の辛さを分かち合ったり、情報交換をしたり。私と同年配で、結婚前に健診を受けたらガンが見つかったという境遇の方もいました。みんな、それまでの生活を突然断ち切られてここに来ている。不思議な連帯感がありました。
一歳上の姉が毎日、生まれたばかりの姪と一緒に見舞いに来てくれるのも嬉しいひとときでした。姪は、私が病気だとわかる1か月前に生まれたんです。赤ちゃんを見るたび励みになって、前向きな気持ちが生まれました。
そんな中で芽生えたのが、『もとの生活』への思いです。当たり前に過ごしていた日常生活は全然、当たり前ではなかった。いかにあの日々が大事なものだったか気づいて、『取り戻したい』と切実に思いました。
1クール目が終わって退院するとき、先生に聞いたのは『ストーマをつけながら、仕事に復帰できますか?』ということです。
事務職として勤めていた職場は、発病に伴い休職中。でも上司は『きっと戻っておいで、待ってるから』と力強い言葉をくれていました。あの場所にきっと戻るんだ、と心に決めていたのです」
薬剤性腸炎で生命が危ぶまれる
しかしその後訪れたのは、さらなる危機。家に戻り、通院しながら2クール目の抗がん剤を始めた2006年1月、中村さんは生死の境をさまよいます。

「副作用があまりに激しく、薬剤性腸炎に…。下痢で脱水に陥り、病院に搬送されました。意識がもうろうとしていたので記憶がないのですが。後に聞くと、命が危ない状態だったそうです。
でも、私自身は前向きでした。意識が戻ったあと考えていたのは、病院の売店にある『つぶつぶみかん』のジュースのこと(笑)。早く回復してあのジュースを飲むぞ!と。ここでも、たわいもないことが強い目標になりました。
もう一つ決めたのは、抗がん剤をやめることです。先生によると、継続しても再発の確率はゼロにはならないとのこと。ならば、こんな危険な目に合ってまで続けたくはないと思いました。その後は飲み薬だけで治療を継続。望み通り、仕事にも復帰しました」
肺への転移と、4度の手術
治療しながら復職し、「普通の生活」を送るなかでは、苦労もあったと振り返る中村さん。

「人工肛門はやはり大変でした。私のストーマは、腸の一部を脇腹から外に出して、そこに袋を付けたタイプ。食事をすればすぐパンパンでトイレにいかなくてはならず、それが嫌で食事をあまりとらなくなりました。47キロだった体重は、一時は36キロまで落ちました。
ストーマが取れたのは3月で、これが2度目の手術です。あのときは、まさか3度目、4度目があるとは思いませんでした。
2007年、両方の肺に転移が見つかって、片方ずつ2回に分けて手術することになりました。
再び、不安が襲ってきました。病院への行き帰りと待ち時間が本当に辛かったです。体重も筋力も落ちている私にとって、かなりの重労働。待合室では、『あと5年生きられないかもしれないのに、2時間空費してる』なんて思ったものです」
10年続いた「ロシアンルーレット」
2007年以降は、通院しながら経過観察。しかし、不安はなかなか消えませんでした。

「腸のガンになったら次は肺、その次が脳、というのが転移の典型的パターンだとよく言われるのですが、『次』を思うと怖くて。3か月に一度、ロシアンルーレットをしているような気分でした。
それが終わったのは、10年後の2017年。先生が、『今後ガンが見つかっても、それは転移ではなくて新しいものだね』とおっしゃったんです。
そして次の回で、『もう通院の必要ナシ』と言っていただけました。何が幸いしたのかは、自分でも今もわかりません。病院での治療のほかにも、同病の仲間と情報交換しながら漢方も飲んでいたし、温泉にも行ったし…いずれにせよ『大丈夫』と思えるようになったのは、本当にここ1~2年です」
心の回復につながった一言
最後の手術からの十数年は、心に負ったダメージを取り除く過程でもありました。
「手術後、始めたのは運動です。スポーツ好きだったので、身体を動かすことは『もとの生活』を取り戻すことでもありました。
2013年にはホノルルマラソンに出場。この大会はもともと、病気になった人の回復を目的として始められたものだと聞き、私にぴったりだと思いました。
ここで走ることで区切りがつく、と考えて走ったら、もう一度走りたくなって、結局2014年にも出場しました。
当時は、区切りをつけたい思いと、再発への心配が入り混じった状態。それが吹っ切れたのは、通っていたヨガの先生の言葉のおかげです。
『心配なのはわかるけど、その出来事は、今じゃないでしょう?』。
ガンになったのは何年も前、再発はまだ起こっていないこと。過去や未来ではなく『今』に意識を向けることが大切だ、と。あのひとことを機に、心身共に回復していった気がします」

「当たり前のありがたさ」をかみしめて
元気を取り戻した中村さんは今、どんな生活を送っているのでしょうか。
「あれから15年。赤ちゃんだった姪も中学生になり、私は42歳になりました。今も仕事を続けながら、ヨガもマラソンも継続、次はニューヨークマラソンが目標。『もとの生活』を求めてきたつもりが、前よりアクティブかも(笑)。
もっと変わったのは食生活です。昔は、何も食べずに運動だけしたり、甘いものとコーヒーを食事代わりにしたりと無茶をしていました。今は和食系、それもプラントベース(植物性)中心。身体をきちんといたわろう、と意識しています。
これは病気をしたからこそ得られた心がけ。今、病気でない人も、どうぞ体を大事にして、と伝えたいですね。その思いから去年、健康的なライフスタイルをアドバイスできる、『ヘルスコーチ』の資格も取得しました。
健やかな体という『当たり前』を多くの方が保てるよう、私も微力ながら支えになれたらと思っています」

※このインタビューは、あくまで中村さんご本人の闘病体験をもとに作成しています。治療法や副作用などには個人差があるため、医療情報に関しては主治医に相談してください。記事の内容は取材時(2020年11月)時点のものです。
撮影/福島章公 取材・文/林 加愛
[ 著者 ]